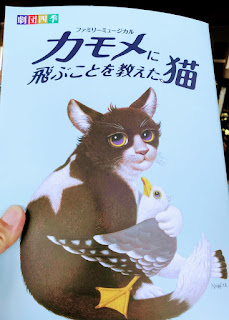先月はミュージカル『アニー』仙台公演を観劇しました。ダフィ役でSCSミュージカル研究所出身の朝日美琴さんがご出演ということもあり研究所の皆と応援。美琴さんはもとより各分野において私共SCS出身者の活躍は頼もしく、嬉しいものです。
来月は、劇団四季ミュージカル『ジーザス・クライスト=スーパースター』を観るために東京エレクトロンホール宮城(宮城県民会館)を再び訪れる予定です。劇団四季には現役で5名ほどSCS出身の俳優が在籍し様々な作品で活躍しています。SCS芸術監督の梶賀千鶴子さんの作品の上演されているということもあり、たいへん縁の深い劇団です。
さて、宮城県民会館は、四季をを通じて仙台の様々な野外イベントの会場ととなる美しい定禅寺通りに位置しています。1964年の開館だというから、今年で還暦の建物です。そのステージには、私も何度か立たせて頂いたということもあって、個人的にも愛着のある会館。そのたたずまいが定禅寺通りのケヤキ並木と実にマッチしているように思うのは、単に見慣れてしまったせいだけとは思えません。文化は身体に内在されていくものと常々思っておりますが、劇場とその面する通りや周囲の雰囲気は人々の記憶としてこの60年で深く刻まれてきている気がいたします。
愛着のあるこの劇場も移転が決まっています。新しい宮城県民会館は、2028年度完成を目指して仙台市青葉区から宮城野区へと移り来年度に着工されると聞いています。計画は県のホームページなどで見られるようですが、新しいホールが人々にこんどはどんな記憶とにぎわいを生み出していってくれるのか、今から楽しみです。